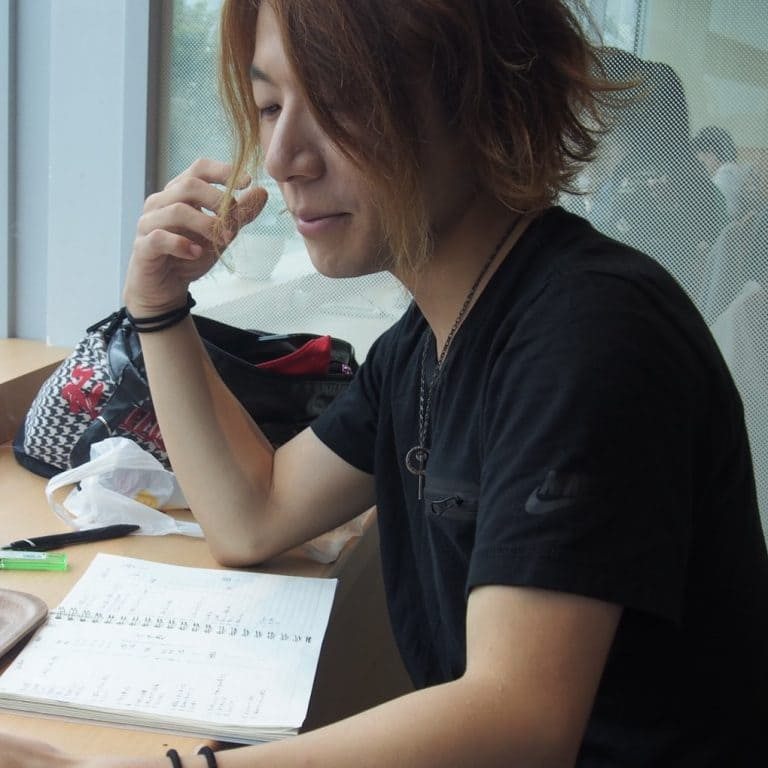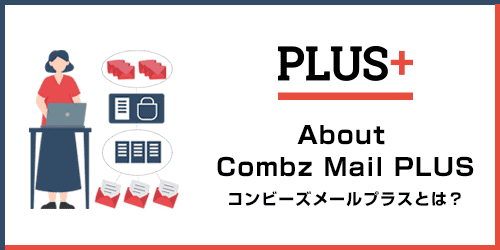BIMI(ビミ)とは?メール一覧にロゴを表示させて信頼性と開封率を高めよう!
2025年10月16日

日々大量に送受信される企業メールにおいて、「なりすまし」や「フィッシング」のリスクは深刻化しています。
「受信者が怪しんで開封をしてくれない」
「メルマガが迷惑メールフォルダに振り分けられる」
たとえSPF/DKIM/DMARCといった送信ドメイン認証技術を導入済みであってもこんな悩みを抱えてしまう。そんなメルマガ担当者の方も少なくないかと思います。
今回解説させていただくBIMI(Brand Indicators for Message Identification)は、この課題を解決するための最新技術です。
BIMIは、メールのセキュリティを確保するDMARCの仕組みを基盤としつつ、企業のブランドロゴをメールの送信元欄に表示することで、受信者に「このメールは本物だ」という視覚的な安心感を提供します。
そこで今回は技術志向のメルマガ担当者に向けて、BIMIの技術的な仕組みから、マーケティング上の具体的なメリット、導入時の具体的な手順と障壁などを徹底解説します!
この記事では、実際の画面のスクリーンショットを豊富に交えながら、私がどのようにメルマガを作成・配信しているのかを具体的にご紹介します。
メルマガ初心者の方から、現在のツールに満足していない方まで、ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです!
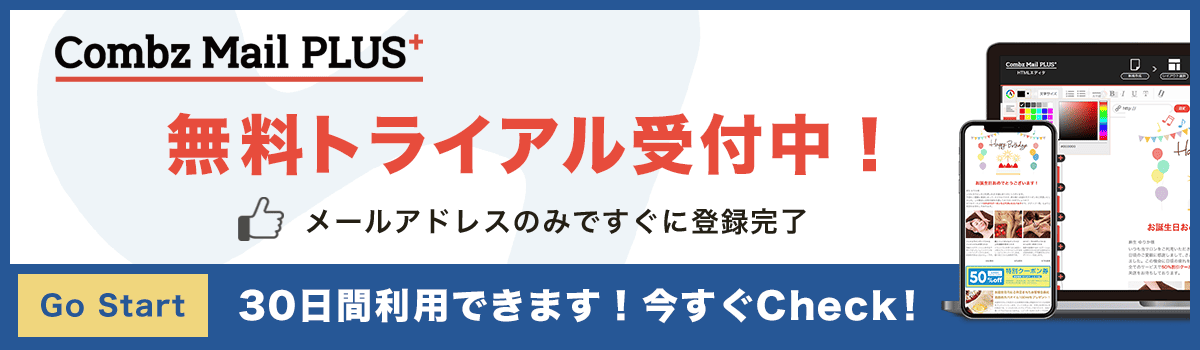

無料で利用できるツールから、高機能な有料ツールまでについてはこちら
関連記事【2024年最新】もう迷わない!あなたにぴったりのメール配信システムを見つけよう!
- 1BIMI(ビミ)とは?
- 1.1SPF/DKIM/DMARCとの関係性
- 2導入によるメリット
- 2.1開封率・クリック率の向上につながる
- 2.2フィッシング対策としての役割
- 2.3ブランド認知と差別化効果
- 3BIMI導入のデメリット
- 3.1導入費用と継続的な維持コスト
- 3.2技術的な障壁がある
- 3.3効果の範囲が限定的である
- 4BIMI導入の流れ
- 4.1必要な前提条件(DMARC設定・ロゴファイル・証明書)
- 4.2実際の導入ステップ(設定~表示確認)
- 4.3導入時によくあるつまずきと解決策
- 4.3.1DMARCポリシーの未達
- 4.3.2ロゴファイルとVMCの問題
- 5将来を見据えた活用
- 5.1BIMIの普及状況と今後の対応メールクライアント
- 5.2メールマーケティング戦略における位置づけ
- 6まとめ
- 7この記事を書いた人
- 8コンビーズメールプラス
- 8.1サービスの特徴
目次
BIMI(ビミ)とは?
BIMIは「Brand Indicators for Message Identification」の略で、メール受信箱の送信元表示欄に、企業やブランドのロゴをアイコンとして表示させるための技術規格です。
その最大の目的は、送信元が正規の企業であることを視覚的に証明し、受信者に安心感を与えることにあります。
BIMIは、単にロゴ画像をメールに添付するのではなく、送信元のドメイン名とロゴ画像を紐付けるための仕組みとして機能します。
具体的には、送信ドメインのDNSサーバーに「BIMIレコード」と呼ばれるTXTレコードを追加します。
このレコードには、表示したいロゴ画像(特定の要件を満たすSVG形式)がホストされているURLや、ロゴの正当性を証明するVMC(Verified Mark Certificate:認証マーク証明書)のURLが含まれます。
メールが受信側に届くと、受信側のメールサービス(Gmail、Yahoo! Mail、Apple Mailなど)は、DMARC認証が成功していることを確認した後、このBIMIレコードを参照します。
またこのような主要なメールクライアントでは、ロゴの不正利用を防ぐため、VMCの取得が必須とされています。
VMCは、公認された認証局を通じて、そのロゴが正式に商標登録されていることを証明する電子証明書です。
これにより、悪意ある第三者によるなりすましメールにブランドロゴが表示されることを防ぎ、ブランド保護を徹底しています。
この厳格な認証プロセスこそが、BIMIが単なるマーケティング施策に留まらない、セキュリティ基盤に基づいた信頼性強化策であることの証です。
SPF/DKIM/DMARCとの関係性
BIMIは、既存のメール認証技術であるSPF(Sender Policy Framework)、DKIM(DomainKeys Identified Mail)、そしてDMARC(Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance)の3つが完全に整備されていることを前提としています。
これらの技術は、メールの「なりすまし」や「改ざん」を防ぐための基本的なセキュリティ対策であり、BIMIは、これらの技術によって担保されたメールの正当性を視覚的に伝えるための「上乗せ技術」と位置づけられます。
このなかでも、BIMIの実装において特に重要なのがDMARCです。
DMARCは、SPFとDKIMの認証結果に基づき、メールの送信元ドメインと差出人ドメインの一致(アライメント)を確認し、認証に失敗した場合の処理方針(ポリシー)を受信側に指示する仕組みです。
主要プロバイダ(Gmail, Yahoo!など)においてBIMIロゴを表示させるためには、DMARCによる認証に合格することが必須条件であり、さらにDMARCポリシーを「p=quarantine」(隔離)または「p=reject」(拒否)のいずれかに設定することが求められます。
これは、ポリシーが「p=none」(監視のみ)の状態では、そのドメインからのなりすましメールがブロックされる保証がないため、BIMIによるロゴ表示が許可されないためです。
導入によるメリット
BIMIの導入には以下のようなメリットがあります。
- 開封率・クリック率の向上につながる
- フィッシング対策としての役割
- ブランド認知と差別化効果
それぞれについて詳しくみていきましょう。
開封率・クリック率の向上につながる
BIMIの導入はメール配信基盤の信頼性を向上させるだけでなく、メールマーケティングの成果に直結するエンゲージメント指標の改善という大きなメリットをもたらします。
受信トレイに企業のブランドロゴが視覚的に表示されることで、顧客はメールを開封する前に、「このメールは自分が知っている、信頼できる企業から送られたものだ」と瞬時に認識できるようになります。
この視覚的な安心感は特に情報過多でメールが埋もれがちな現代の受信箱において、メールが未開封のままスキップされるのを防ぐ強力な要因となります。
海外の早期導入企業を対象とした調査では、BIMIによってメールの開封率が平均で10%から、高いケースでは39%近く向上したという報告が複数出ています。
またBIMIはクリック率(CTR)の向上にもつながります。
信頼できる送信元からのメールだと認識されているため、メール内のコンテンツやCTA(Call to Action)に対する信頼度も高まり、受信者がリンクをクリックして次のアクションへ進む心理的なハードルが大きく下がります。
フィッシング対策としての役割
BIMIが提供する最大の価値の一つは、技術的な裏付けに基づいた視覚的なフィッシング・なりすまし対策としての役割です。
BIMIのロゴを表示する前提条件として、送信ドメイン認証技術であるDMARCのポリシーを「隔離(p=quarantine)」または「拒否(p=reject)」に設定することが必須とされます。
つまり、BIMIロゴが表示されているということは、そのドメインが既に厳格なセキュリティ対策を講じていることの視覚的な証明となります。
フィッシングメールの手口は年々巧妙化し、送信者名や件名だけでは正規のメールと見分けるのが非常に困難になっています。
しかし、BIMIが適用されたメールには、認証マーク証明書(VMC)によって真正性が証明されたブランドロゴが表示されます。
もし悪意ある第三者がドメインを偽装してなりすましメールを送ったとしても、そのメールはDMARC認証に失敗するため、受信箱でBIMIロゴが表示されることはありません。
受信者は、ロゴの有無という明確で直感的な指標によって、一目で正規のメールと不正なメールを区別できるようになります。
企業側にとっては、顧客がフィッシング詐欺の被害に遭うリスクを低減し、ブランドイメージが毀損されることを未然に防ぐという、極めて重要なセキュリティメリットを提供します。
ブランド認知と差別化効果
BIMIの導入は、ブランド認知に繋がる強力な一手だといえます。
顧客の受信トレイは、日々数十、数百通のメールで溢れかえっており、その中で自社のメールを埋もれさせないことがマーケティングにおいて重要です。
BIMIによるブランドロゴの表示は、メールが開封される前の段階で、競合他社のメールよりも視覚的に目立ち、強い存在感を示すことを可能にします。
この視覚的なアピールは、顧客とのエンゲージメントを高めるだけでなく、ブランド想起率の向上にも大きく寄与します。
顧客はメールをスクロールするたびに自社のロゴを目にすることになり、広告費を投じることなく、継続的にブランドを印象づける効果が得られます。
特に、多くの企業が未だBIMI導入の途上にある現状では、ロゴが表示されているという事実そのものが、先進的なセキュリティと顧客体験への投資を行っている企業であるというポジティブなメッセージを市場に発信します。
BIMI導入のデメリット
BIMIの導入はメール配信基盤の信頼性を飛躍的に向上させますが、技術志向の担当者として、以下のようなデメリットがあることを事前に把握しておくことが重要です。
- 導入費用と継続的な維持コスト
- 技術的な障壁がある
- 効果の範囲が限定的である
それぞれについて、詳しくみていきましょう。
導入費用と継続的な維持コスト
BIMIロゴの真正性を保証するVMC(Verified Mark Certificate:認証マーク証明書)の取得は、特にGmailのような主要なメールサービスでのロゴ表示に実質的に必須とされています。
このVMCの発行には認証局への申請費用がかかり、一般的には年間で数十万円程度(約20万~30万円が相場)の継続的なコストが必要となります。
さらにVMC取得の前提として、表示したいブランドロゴが商標登録されていることが求められ、未登録の場合はその手続きにかかる時間と費用も発生します。
また技術部門の工数として、DMARCやBIMIレコードの設定・監視、ロゴファイルのメンテナンスといった運用工数も考慮に入れる必要があります。
技術的な障壁がある
BIMIの要件を満たすためにDMARCポリシーを「p=quarantine」(隔離)または「p=reject」(拒否)に強化する際、認証に失敗した正規のメールが顧客に届かなくなるリスクを避けるため、DMARCレポートに基づく慎重な分析と段階的なポリシー強化が必要です。
さらに、表示させるロゴ画像は、セキュリティと互換性のためにSVG Tiny Portable/Secure (SVG Tiny PS)という厳密な規格に準拠する必要があり、単に一般的なSVGファイルを用意すれば良いわけではありません。
効果の範囲が限定的である
BIMIは業界標準として普及途上にあり、現時点ではGmail、Apple Mailなど一部の主要メールクライアントやプロバイダのみが対応しています。
したがって、BIMIを設定しても、全ての顧客の受信箱でロゴが表示されるわけではなく、メールの開封率や信頼性向上といったメリットを享受できる顧客層には限りがあるため、投資対効果を判断する際にはその点を正確に把握することが求められます。
BIMI導入の流れ
ここではBIMIを実際に導入する際に必要なことや流れについて、解説します。
必要な前提条件(DMARC設定・ロゴファイル・証明書)
繰り返しになりますが、BIMIの導入では既存のメールセキュリティ基盤が確立されていることを大前提とします。
まず、メールの真正性を保証するSPF(Sender Policy Framework)とDKIM(DomainKeys Identified Mail)が、送信ドメインのすべての送信元で適切に設定されている必要があります。
その上で、BIMI導入の核心となるのがDMARC(Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance)です。
ロゴを表示させるためには、DMARCのポリシーを「p=none」(監視のみ)から「p=quarantine」(隔離)または「p=reject」(拒否)のいずれかに強化し、かつDMARC適用率を示すpctタグを100%に設定しなければなりません。
これにより、なりすましメールが確実にブロックされる状態を担保します。
次に、表示させるロゴの準備です。
ロゴは、高いセキュリティと互換性を確保するため、一般的なSVGファイルではなく、厳格な要件を満たしたSVG Tiny Portable/Secure (SVG Tiny PS)形式で作成し、HTTPSでアクセス可能な公開ウェブサーバーにホストする必要があります。
そしてロゴが企業によって正式に所有されていることを証明するために、公認の認証局からVMC(Verified Mark Certificate:認証マーク証明書)を取得します。
VMCの発行には、ロゴが日本やWIPO(世界知的所有権機関)加盟国で商標登録されていることが必須条件となるため、この手続きがBIMI導入における最も時間とコストを要するステップとなります。
実際の導入ステップ(設定~表示確認)
BIMI導入は、前提条件の整備が完了した後、主にDNSレコードへの情報登録と動作確認という工程に進みます。
前述の準備が整ったら、それらの情報をDNSサーバーのTXTレコードとして公開します。
この公開するレコードをBIMIレコードと呼び、通常は
<セレクタ>._bimi.<ドメイン名>
という形式で設定します。
セレクタには「default」を使用することが一般的です。
BIMIレコードには、BIMIのバージョンを示す「v=BIMI1」に加えて、ロゴファイルのURLを指定する「l=タグ」と、VMCの証明書ファイルのURLを指定する「a=タグ」を記述します。
例えば、
default._bimi.example.com IN TXT "v=BIMI1; l=https://example.com/logo.svg; a=https://example.com/vmc.pem"
といった記述を行います。
DNSレコードの公開後、対応しているメールクライアント(Gmail、Apple Mailなど)でテストメールを送信し、ロゴが意図通りに表示されるか、またDMARC認証が正しく機能しているかを確認します。
DNS情報の伝播やメールクライアント側のキャッシュによってロゴが表示されるまでに時間がかかる場合があるため、表示確認は数日間にわたって行う必要があります。
導入時によくあるつまずきと解決策
BIMI導入において、いくつかの技術的・手続き的なつまずきやすいポイントを事前に知っておくことがプロジェクトの遅延を防ぐ鍵となります。
DMARCポリシーの未達
BIMIロゴが表示されない場合、DMARCポリシーが「quarantine」または「reject」になっていないか、あるいは「pct=100」になっていないことが原因として考えられます。
解決策として、DMARCレポートを継続的に分析し、認証失敗の原因となっている正規の送信元を特定し、SPFやDKIMの設定漏れがないかを修正することが不可欠です。
ロゴファイルとVMCの問題
ロゴファイルがSVG Tiny PSの厳密な規格を満たしていない、またはHTTPSではないサーバーにホストされている場合、ロゴは表示されません。
またVMCの証明書ファイルに不備がある、またはBIMIレコード内のURLが間違っている場合も表示失敗の原因となります。
解決策は、ロゴがBIMI規格を満たしているか検証ツールで確認し、VMCが認証局によって承認されているかを確認した上で、DNSレコードのlタグとaタグに記載されたURLが正しくアクセスできるかを検証することです。
これらの要件は技術的に厳密であるため、導入時にはDMARCレポートツールやBIMI検証サービスを活用し、問題を切り分けていくことが成功への近道となります。
将来を見据えた活用
最後に、BIMIという技術における将来のあり方について考察してみましょう。
BIMIの普及状況と今後の対応メールクライアント
BIMIは比較的新しい規格であるものの、メールセキュリティとブランド保護の観点から国際的に注目されており、その普及は着実に進んでいます。
日本国内においても、主要なメールサービスプロバイダでの対応が進んでおり、現在ではGmail、Apple Mail(iCloudメール)、auメール、ドコモメールといった高いシェアを持つサービスやアプリでロゴ表示が可能になっています。
特に、技術的な要件が厳しくコストもかかるVMC(認証マーク証明書)の取得を前提としているにもかかわらず、BIMI導入を完了する国内企業は増加傾向にあります。
今後の見通しとして、BIMIに対応するメールクライアントやプロバイダはさらに拡大していくことが予測されます。
これはフィッシング詐欺やなりすましメールの被害が深刻化する中で、受信者側がメールの正当性を簡単に判断できる視覚的な認証の必要性が高まっているためです。
メールマーケティング戦略における位置づけ
BIMIは、単なるセキュリティ技術ではなく、メールマーケティング戦略における差別化の要として位置づけられます。
多くの企業がメール配信を行う中で、受信トレイでの「見え方」をコントロールし、競合よりも優位に立つための貴重なツールです。
ロゴの認証を通じて、企業全体のセキュリティ意識と技術力を顧客にアピールできるため、これは攻めのマーケティング施策であると同時に、企業のリスク管理体制を示すブランディング施策でもあります。
まとめ
BIMI(Brand Indicators for Message Identification)は、メールセキュリティの国際標準であるDMARCの厳格な認証プロセスを基盤に、企業のブランドロゴをメール受信トレイに表示させる画期的な技術です。
これは単なるロゴ表示機能ではなく、「DMARCによる技術的な正当性」を「ロゴという視覚的な信頼性」に変換する仕組みであり、現代のメールマーケティングとセキュリティ戦略における最重要テーマの一つです。
今回の記事をきっかけにBIMIを導入して、メルマガの信頼性を上げるとともに、より効果的なメールマーケティングに繋げてみてはいかがでしょうか?
この記事を書いた人
コンビーズメールプラス
かんたん・安心・低価格のメール配信システム

「コンビーズメールプラス」は、簡単操作、充実したサポート、そして低価格が魅力のメール配信システムです。
初心者の方でも安心して使い始めることができます。
サービスの特徴
- 費用対効果:費用対効果が高いメールマーケティングサービス
- ノウハウ:売り上げアップのノウハウ集が充実
- アフターフォロー:運用に添った提案や相談が受けられる
配信数無制限で低価格なプランが用意されているため、コストパフォーマンスに優れています。 初期費用0円、月額5,500円から利用可能。充実したレポート機能も魅力のひとつです。
開封率、クリック率、コンバージョン率などのデータを分かりやすく表示し、分析することができます。
セキュリティ対策も万全で、最安プランでもSPF認証に対応しています。
「MAシステムは難しそうで使いこなせるか不安…だけど、メルマガには力を入れていきたい!」
そんな方におすすめのメール配信システムです。
| 初期費用 | 0円 |
|---|---|
| 価格 | 1,000アドレス:5,500円/月~ |
| 割引・キャンペーン | 要問い合わせ |
| 無料トライアル | 最長30日間(100アドレス100通まで) |
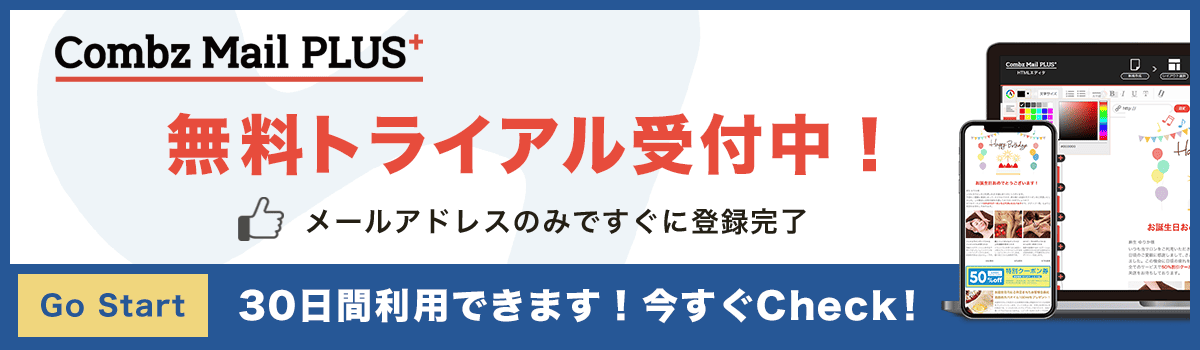
資料請求・お問い合わせ
料金プランや運用のご相談まで、あなたの専属コンサルタントがサポートします
パートナー制度
コンビーズのサービスをご紹介していただくと、あなたも紹介者さんもおトク
セキュリティ
お客様が安心してご利用いただけるようセキュリティ対策もバッチリ。第三者認証であるISMS(ISO27001)を取得済み。