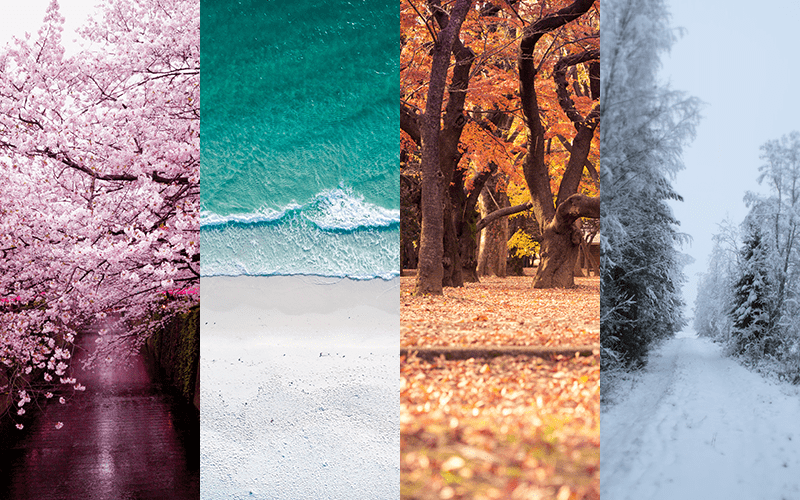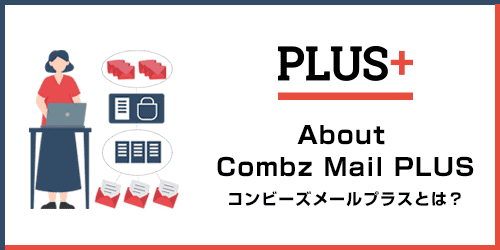【メルマガネタ】季節や気候の語源について知っておこう!
2021年07月01日
4つの季節の語源
まずは4つの季節の語源から紹介します。といっても、これらには諸説あるものが多く、これが絶対というわけではありません。ただ、昔の人はロマンチックな人が多かったようで、語源を調べていると、当時の情景が目に浮かぶような気がします。
春
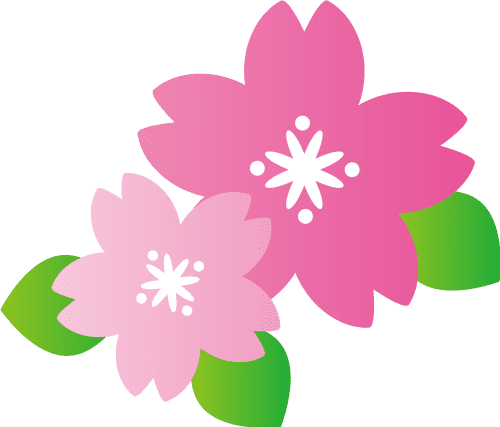
「春」はひらがなに直すと「はる」となり、ここにヒントがあるようです。由来として挙げられるのは大きく分けて2つ。
- 春になると、草木の根が「張る」ということ。
- 春の季節は天候が「晴る」ことが多いからだそうです。
夏
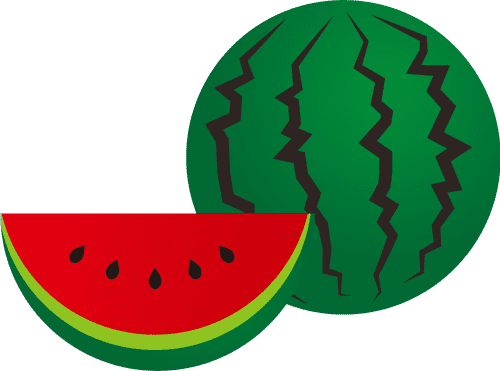
「夏」もひらがなに直してみると「なつ」です。そして、夏は3つの由来があります。
- 作物が木や畑に「なる」から
- とても「あつ」いから
- 太陽の光でさまざまなものが「ねつ」を帯びるから
どれも直接「なつ」と言っているわけではありませんが、音が似ていますね。
秋
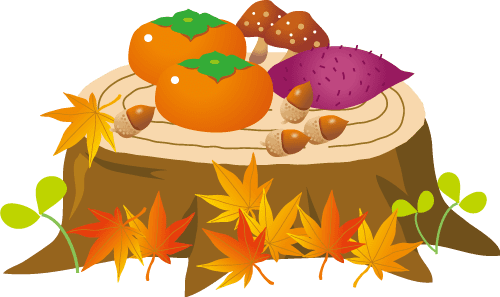
「秋」はどんな語源なのでしょうか。秋にも3つ由来があります。
- まだ夕方になっても空が明(あき)らかだから
- 作物が枯れて飽き(あき)ていくから
- 紅葉などで木々の葉が赤(あか)くなっていくから
秋は比較的イメージしやすいのではないでしょうか。漢字にも火が入っており、木が燃えるように赤くなってく様を表していますね。
冬
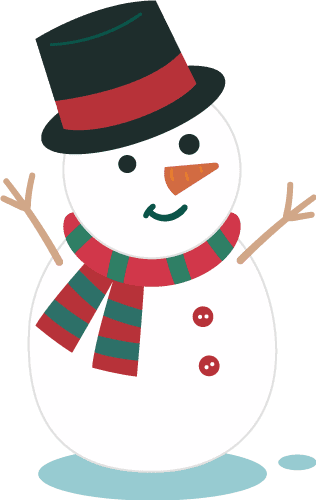
最後に「冬」です。こちらも3つ紹介します。
- 気温が下がって冷ゆ(ひゆ)るから
- 寒くて体が震(ふる)えるから
- 雪が降る(ふる)から
といったものがあります。どれも少し「ふゆ」というには遠い気もしますが、趣を感じます。
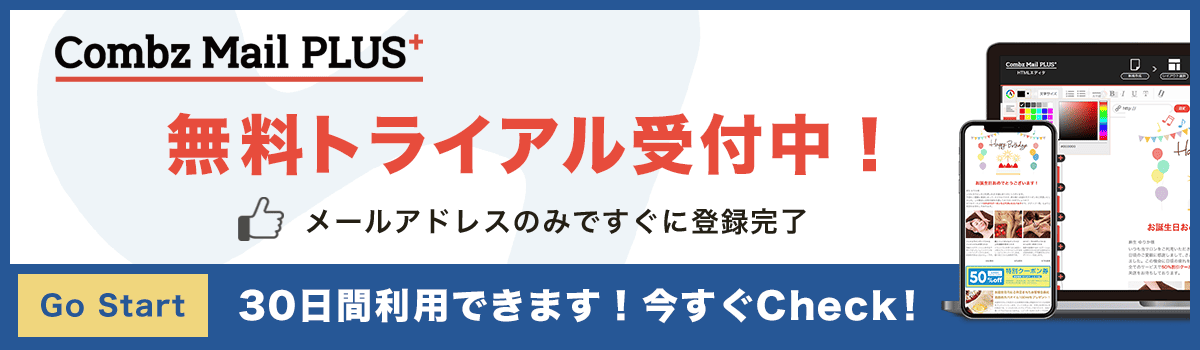
気候の語源
季節以外に「気候」という言葉がありますが、実は気候自体にも由来があるのです。「気」は二十四節気の気、「候」は七十二候の候から取ったものですが、あまり耳馴染みがない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
二十四節気
二十四節気は、四季よりも細かく1年の移り変わりを表した呼び方として作られました。1年を4等分した四季では区分が大きすぎるため、農業や漁業をして働く人は、時期を言い表しにくかったためです。
- 立春:春の始まりの日
- 夏至:昼が最も長く、夜が最も短くなる日
- 秋分:秋の彼岸の中日で、昼夜の長さがほぼ同じになる日
- 冬至:夜が最も長く、昼が最も短くなる日
このような呼び方は聞いたことがあるのではないでしょうか。これらが全部で24通りあり、各季節をさらに六等分しています。
七十二候
二十四節気をさらに三等分したのが七十二候です。
七十二候には
- 黄鶯睍睆(うぐいすなく)
- 雀始巣(すずめはじめてすくう)
- 牡丹華(ぼたんはなさく)
- 寒蝉鳴(ひぐらしなく)
というものがあり、名前の通り全部で72種類の呼び方があります。ただ、こちらはあまり馴染みがないかもしれません。古代中国の宣明暦にも似たようなものがあり、動物の動きや植物の移り変わりを表すように作られました。
まとめ
今回は四季や気候の由来についてまとめてみました。これらの話題をメルマガの導入文として記載しておくと「そうなんだ、ためになるな」といった印象を与えることができ、本文も読んでもらえる可能性が高まります。
ぜひ、メルマガを作成する際には、このような雑学ネタや役立つ情報を取り入れてみてはいかがでしょうか?
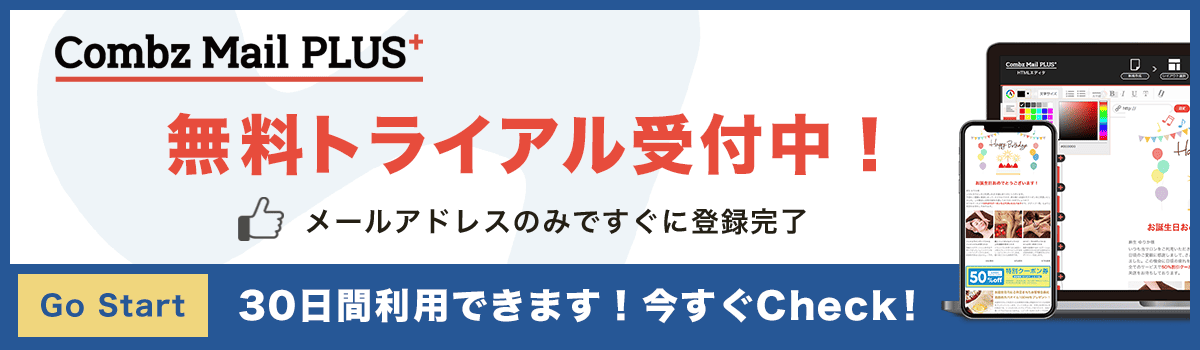
資料請求・お問い合わせ
料金プランや運用のご相談まで、あなたの専属コンサルタントがサポートします
パートナー制度
コンビーズのサービスをご紹介していただくと、あなたも紹介者さんもおトク
セキュリティ
お客様が安心してご利用いただけるようセキュリティ対策もバッチリ。第三者認証であるISMS(ISO27001)を取得済み。