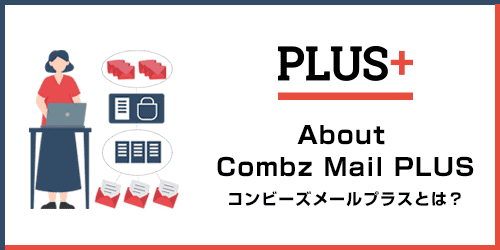メーラーとは?種類などの解説&ビジネスにおすすめのメーラーを紹介!
2023年08月25日
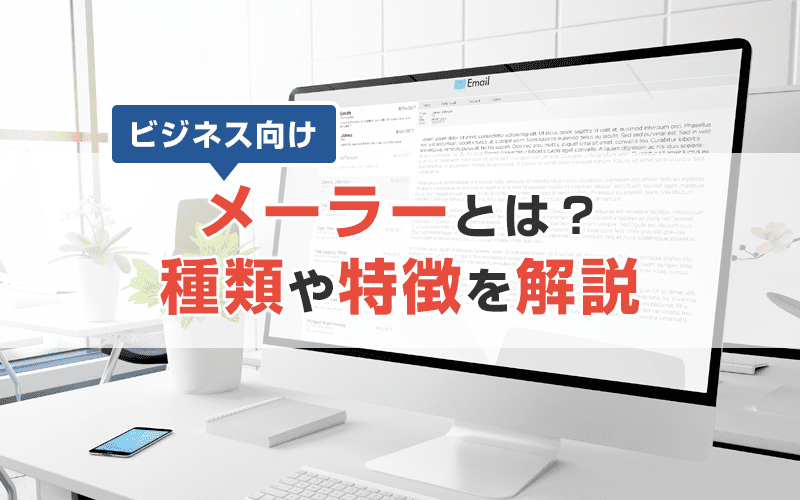
メーラーとは、メールの送受信を行うことができるソフトウェアのことを指します。プライベートのメールだけでなくビジネスシーンでも活躍し続けているツールです。
近年では、SNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)の普及により、SNSを通じてのコミュニケーションが当たり前となっています。しかしながら特にビジネスにおいては、今でもメールでのやり取りが欠かせないという方は、たくさんいるのではないでしょうか?
そこで今回は『メーラーとは?種類などの解説&ビジネスにおすすめのメーラーを紹介!』と題して、メールのやり取りに欠かせないメーラーについて紹介します。
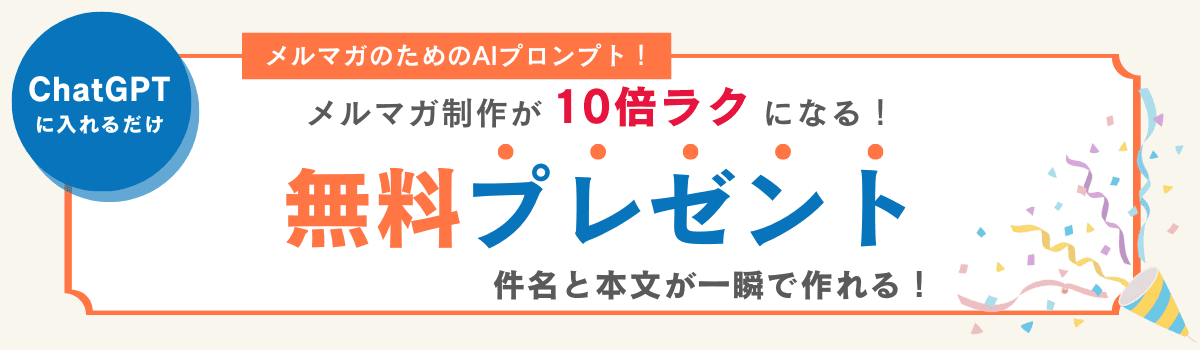
▲メルマガ業務を、出来るだけラクに▲

「メルマガの読者像を想定する」「メルマガ登録者を増やすための集客方法」「メルマガを運用するにあたっての目標設定」などについてはこちら
関連記事メルマガの始め方が分からない!初心者でもすぐにできる事前準備とは
- 1メーラーとは一体何か?
- 1.1メールソフトとは何か?について解説
- 1.2メーラーのメール送受信の仕組み
- 1.3メーラーの役割
- 2メーラーの種類はメールソフトとWebメール
- 2.1メールソフトとは何か?について解説
- 2.2Webメールとは?どんなものか紹介
- 3メーラーのメリットとデメリット
- 3.1代表的なWebメールのメリット・デメリット
- 3.1.1Outlook
- 3.1.2Thunderbird
- 3.2代表的なWebメールのメリット・デメリット
- 3.2.1Gmail
- 3.2.2Yahoo!メール
- 4ビジネスシーンでのメール利用割合
- 5メーラーの選び方を解説!
- 5.1メーラーを導入する前に課題をあぶりだす
- 5.1.1メールの対応ミスが発生しにくいこと
- 5.1.2メールを探しやすいこと
- 5.2ビジネス環境に応じてメーラーを決める
- 5.2.1メールの利用頻度
- 5.2.2デスクワークの頻度
- 6おすすめのメーラーを2つの視点でピックアップ
- 6.1少人数で対応する場合はGmailがおすすめ
- 6.2複数人で対応する場合はMail DealerやRe:lationがおすすめ
- 7まとめ
目次
メーラーとは一体何か?
私たちは、プライベートのみならずビジネスの場面でも、当たり前のようにメールを使用しています。メールのやり取りをするために欠かせないものといえば、メーラーです。
ここでは、いつも利用しているメーラーが、裏ではどのような動きをして送受信をしているかを解説します。
メーラーという単語の意味
メーラーとは、メールを作成したり、送受信や閲覧を行う際に使うソフトウェアのことを指します。
メーラーは主に2種類あり、「メールソフト」と「Webメール」に分類されます。メールソフトとWebメールについては、のちほど『メーラーの種類はメールソフトとWebメール』で詳しく解説します。
メーラーのメール送受信の仕組み
メールが送受信されるまでの過程を、簡単に解説すると以下の通りになります。
- 送信側はメールをパソコンからSMTPサーバへメーラーを使用してアップロード
- SMTPサーバにアップロードされたメールをPOPサーバに移動させる
- 受信者はパソコン上のメーラー画面で、受信メールを確認できるようになる
この仕組みがWebメールの場合だと、サーバに直接アクセスすることによりメールを取得できる仕組みになっています。
メーラーの役割
要約するとメーラーは以下3つの役割を果たしています。
- パソコン上もしくはWeb上でメールを閲覧および作成
- 送信されたメールをSMTPサーバ上にアップロード
- 受信したメールをPOPサーバ上からダウンロード
これら3つの機能だけでなく、さらに多くの機能が追加されているメーラーも数多く存在します。
ちなみに、POPサーバでは単にメールデータをそのままの状態で受け渡すだけなので、メールデータがサーバ上に残ることはありません。しかし、POPではなくIMAPの場合はメールデータをコピーすることによりデータを取得する仕組みなので、サーバ上にメールデータが記録として残ります。
もしバックアップとしてサーバ上にメールデータを残しておきたい場合は、IMAPに対応したメーラーがおすすめです。
メーラーの種類はメールソフトとWebメール
さきほど簡単に紹介しましたが、メーラーは大きく分けると2種類に分類されます。「メールソフト」と「Webメール」の2種類です。ここからは、それぞれどういった特徴があるのかを解説していきます。
メールソフトとは何か?について解説
PCなどのデバイスにインストールして使用するタイプのメーラーを「メールソフト」と呼びます。
オフライン状態のときでも、一度メールをダウンロードしてしまえば閲覧することが可能であることが特徴です。もちろん、メール作成時の下書きもオフライン状態で保存できます。ただ、メールを送受信する際は、インターネットに接続する必要があります。
また、メールソフトはインストールされたデバイスでのみ管理することができます。そのため、複数のデバイスを用いてメール管理をする場合には、不向きとなっています。
例えば、サポートセンターに寄せられたお問い合わせに対して、複数人が対応するというような使い方は難しいでしょう。
Webメールとは?どんなものか紹介
メールソフトに対して「Webメール」は、インターネット環境が整っていれば、どんなデバイスでも、どんな場所であってもアクセスすることができます。
どのデバイスからもアクセス可能なので、デスクワーク時に会社のパソコンでログインして作業していたメールを、外出先でスマートフォンやタブレットで引き続き作業することができます。
注意点としては、オフライン状態ではメールの閲覧や作成ができません。そのため、インターネットに接続できる環境が必須となります。
メーラーのメリットとデメリット
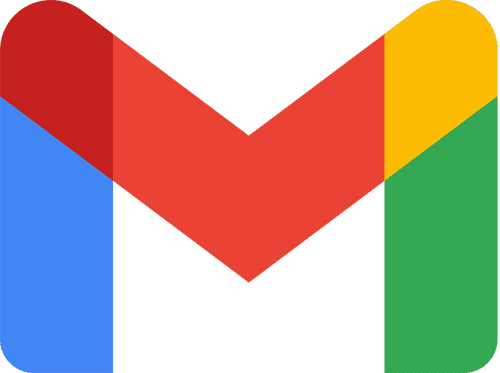
ここでは、代表的なメーラーであるメールソフトとWebメールの、メリットとデメリットについて解説します。
代表的なメールソフトのメリット・デメリット
ここでは、2つの代表的なメールソフトを紹介するとともに、メリットとデメリットについて解説します。
Outlook
Outlook
「Outlook」は、Microsoft社が提供するメールソフトです。
メリット
メリットとしては、他のユーザーとスケジュールを共有する機能が付いていたり、「リマインダー機能」が付随しているので、スケジュール管理が重要なビジネスシーンにおいて使いやすい点があげられます。受信ボックスの操作性に優れている点もメリットといえます。
デメリット
デメリットとしては、「Outlook」の場合、パソコンのスペックが低いと動作が重くなってしまうことがあげられます。
また、デフォルトのメールフォーマットがHTML形式のため、受信するメーラーの種類によっては文章レイアウトが崩れたりするなどの、問題が発生する可能性があります。
Thunderbird
Thunderbird
「Thunderbird」は、インターネットブラウザFireFoxで知られるMozilla Foundation社の子会社であるMZLA Technologies Corporation社が手がけるメールソフトです。
メリット
カスタマイズ性に優れている点が大きなメリットです。「アドオンマネージャー」という管理画面からUI(ソフトウェアの見た目)の変更や拡張機能の追加などを、簡単に行えることがポイントです。また、複数のメールアドレスを同じ画面内で管理できるという点も、大きな利点といえます。
デメリット
カスタマイズの自由度が高いこともあり、使いこなすためには、ある程度の知識が要求されます。
代表的なWebメールのメリット・デメリット
次は、2つの代表的なWebメールの紹介と、それぞれのメリットとデメリットについて解説します。
Gmail
Gmail
「Gmail」は、Google社が提供する無料のWebメールです。
メリット
様々な端末でのアクセスに対応しているため、インターネットへの接続環境さえあれば、どんな場所でもメール作業が可能であることです。
加えて、Gmailのメールアドレスを所持していると、GoogleドライブやGoogleドキュメントといった、Google社が提供している多くのツールを使うことができます。
デメリット
多機能のために操作性が複雑化していることや、アーカイブ機能がわかりにくく、活用しにくい点などがあげられます。
Gmailでは、既読済みのメールを安全な場所に移動させる機能をアーカイブといいます。アーカイブしてしまうと、それまでの受信ボックスでメールを見ることができなくなってしまいます。これにより、アーカイブしただけなのに誤ってメールを削除してしまったと勘違いする人が多いのも事実です。
Yahoo!メール
Yahoo!メール
「Yahoo!メール」は、検索エンジンサイトのYahoo内で使うことができる無料のWebメールです。
メリット
1つのメールアカウントに対して、最大10個のサブメールアドレスが作成できることです。この機能をセーフティアドレス機能と呼びます。複数のアドレスを作成できるので、業務用とプライベート用をはじめ、様々な用途にメールアドレスを分けることができます。
デメリット
メールに広告が表示されてしまう点です。特に管理画面上の広告は表示面積が大きく、わずらわしさを感じる方もいるかもしれません。
また、新着メールが自動で読み込まれないことや、迷惑メールフィルタの精度の低さなどもデメリットとしてあげられます。
ビジネスシーンでのメール利用割合
現在メールはビジネスシーンでどれだけ利用されているのでしょうか?
日本ビジネスメール協会による『ビジネスメール実態調査2023(※)』によれば、最も使われているビジネスシーン上のコミュニケーションツールはメールだそうです。
対象者1,634人に調査を行っているのですが、その内98.53%がビジネス上でメールを使用しており、2番目に電話(82.44%)、3番目にテレビ会議・Web会議(75.52%)という結果となっています。
近年はSNSなどもかなり普及していますが、ビジネスシーンでは圧倒的にメールでのやり取りが多いことがわかります。
メーラーの選び方を解説!
ビジネスシーンでは、今でもメールを使って営業や提案などの連絡を、行っているかと思います。
では、ビジネスにおいてメールのやり取りをする際、メールソフトとWebメールのどちらが使いやすいのか?メーラーを導入する前に確認しておくべきことと、選び方について紹介します。
メーラーを導入する前に課題をあぶりだす
メーラーを導入する前に確認しておくべきことは、基本的に「メールへの対応」です。メールのやり取りをする際に誤った対応をしてしまうと、クライアントへの信用度を下げてしまいます。
まずは、普段使っているメーラーでのメールの対応を見直してみましょう。よくある課題としては、「メールの対応ミス」「目的のメールを探す手間」です。
メールの対応ミスが発生しにくいこと
メーラーを何人かで使用していると起こりえるのは、返信を忘れていたり、対応済みにもかかわらず重複してメールしてしまうことです。
どちらにせよ、誤った対応となってしまうため、クライアントへの信用を損ねる恐れがあります。
このような対応の漏れや重複が発生しないように、メーラーを選ぶ際は受信トレイが管理しやすいものであったり、返信済みかそうでないかが分かりやすいものを使いましょう。
メールを探しやすいこと
通常のメーラーの場合、すでに対応済みのメールかどうかなどを確認するのは手間がかかります。
新規のメールはともかく、過去にやり取りしたメールの内容などを確認する場合は、一度メーラー内で検索をかけて探し出さなければいけません。
誰がいつどんな対応をしたかなどをきっちり情報共有したうえで、メールの探索、内容確認、対応をしなければいけないので、複数人でも簡単に管理ができるメーラーを導入することをおすすめします。
ビジネス環境に応じてメーラーを決める
これまでご紹介したように、メーラーには数多くの種類が存在しています。とはいえ、使うメーラーはだいたい1つに絞り込むのではないでしょうか?メーラーを選ぶ方法の1つとして、ビジネス環境も考慮するとよいでしょう。
メールの利用頻度
メーラーはメールを行う頻度によって、選ぶ基準も変わってきます。
メールのやり取りの頻度が高い方は保存容量が小さいと、すぐに容量がいっぱいになり送受信に支障をきたしてしまいます。あらかじめ、保存容量が大きめのメーラーを用意する必要があります。
逆に利用頻度が低い方は、保存容量は特に気にならないと思いますので、どのメーラーを選んでも特に問題はないでしょう。
デスクワークの頻度
決まった場所でのデスクワークが多い方は、メーラーはメールソフトでも問題ないでしょう。しかし、出先での利用が多い方は、スマートフォンをはじめとした様々な端末でアクセスが可能な、Webメールの方が便利です。
おすすめのメーラーを2つの視点でピックアップ
ビジネス環境だけでなく、メーラーを使用する人数によっても、どんなものを使えばいいかが変わってきます。ここでは、使用する人員の規模に応じておすすめのメーラーを紹介します。
少人数で対応する場合はGmailがおすすめ
独断と偏見にはなりますが、ビジネスにおいてメールの送受信を行う際にはGmailをおすすめします。理由としては、『代表的なWebメールのメリット・デメリット』にも記載したとおり、ビジネスシーンで活躍するためです。
主に役立つ面でいうと、
- Webブラウザ上や専用アプリから手早くメールの確認ができる
- インターネットに接続できれば複数のデバイスから閲覧が可能
- 1つのアカウントでGoogleが提供するあらゆるツールを使うことができる
- セキュリティがしっかりしている
などがあげられます。
Gmailによる顧客へ連絡ができるだけでなく、GoogleMeetを使えばオンラインで営業会議ができたり、Googleドキュメントやスプレッドシートで資料を作成してクラウド上に保存することができます。
メールのやり取りだけでなく、仕事に必要なツールを活用することができるため、ビジネス使用にGmailはおすすめです。
複数人で対応する場合はMail DealerやRe:lationがおすすめ
複数人でたくさんの問い合わせに対し、円滑に対応したい場合は、Mail DealerもしくはRe:lationをおすすめします。
どちらもほぼ同じような機能を備えており、メール、電話、LINEなど、複数の問い合わせ窓口からきた連絡を、1つの画面で管理することができます。
また、双方ともステータス管理されているので、未対応、対応中、対応完了などを一目で把握することができるので、返信漏れや二重対応防止につなげることができます。
まとめ
今回の記事はいかがでしたでしょうか?
メーラーはメール管理や送受信を行える作業台としての役割を持ちます。利用頻度が多い場合は、自分の用途にあっているか、使い勝手がいいかによって大きく業務効率が変わってくるものです。
今一度、ご自身の業務内容を振り返ってみて、業務内容にふさわしいメーラーを選ぶことで、業務効率化を図っていきましょう。
以上、『メーラーとは?種類などの解説&ビジネスにおすすめのメーラーを紹介!』について、ご紹介いたしました。
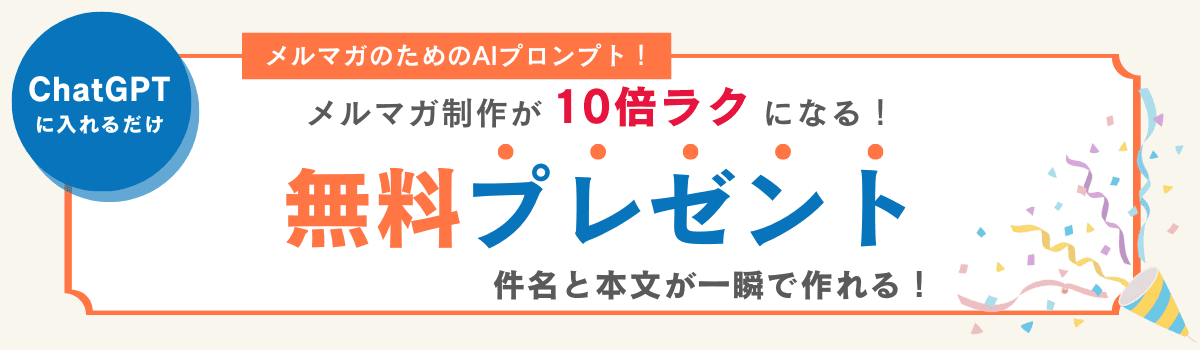
▲メルマガ業務を、出来るだけラクに▲
資料請求・お問い合わせ
料金プランや運用のご相談まで、あなたの専属コンサルタントがサポートします
パートナー制度
コンビーズのサービスをご紹介していただくと、あなたも紹介者さんもおトク
セキュリティ
お客様が安心してご利用いただけるようセキュリティ対策もバッチリ。第三者認証であるISMS(ISO27001)を取得済み。