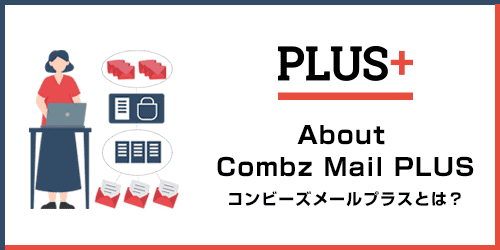Webライティングとは?表記統一、検索キーワードなど意識べきポイントを紹介【応用編】
2022年02月28日
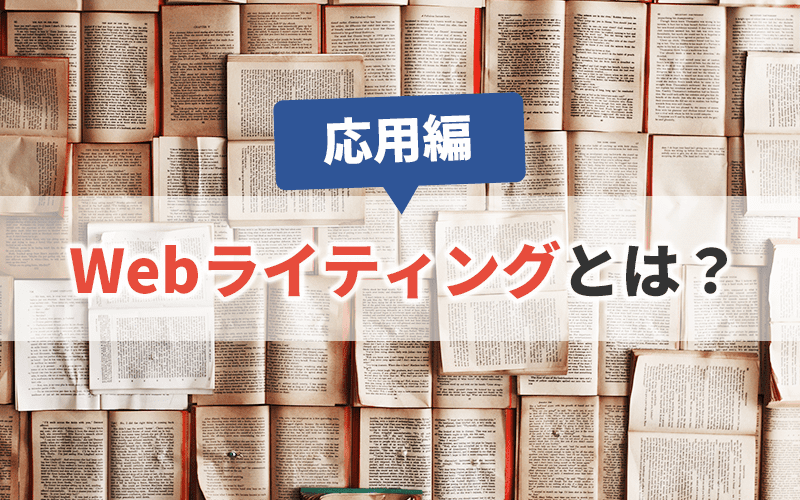
Webライティングに慣れてくると「もっと読みやすい内容にしたい」と、考えるようになります。ただ、商品やサービス、特定のコンテンツの情報が的確に説明されていないと、読んでくれる可能性が低下します。
そこで今回は『Webライティングとは?知れば誰でも書ける!【応用編】』と題して、より伝えやすい方法を解説します。
Webライティングに必要なテクニックを覚えると、ブログ、サイト、メール配信など媒体を問わず、読みやすい文章を提供できるようになります。
まだ、文章がうまく書けないという方は、下記リンクをご参照ください。
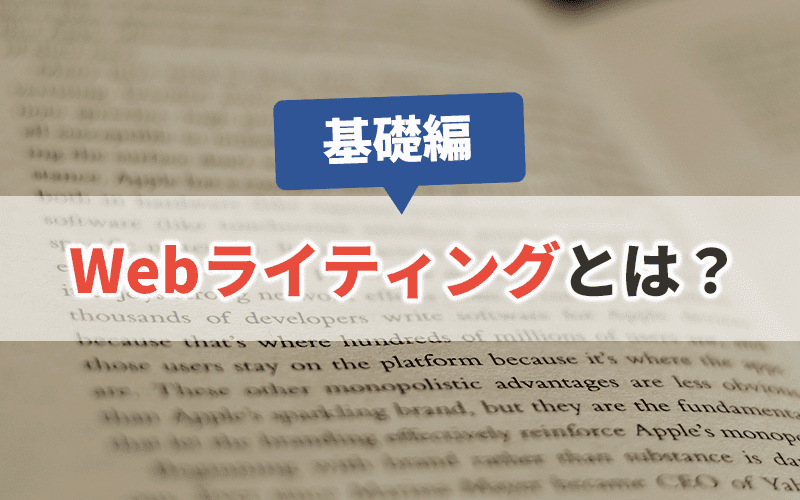
ブログやサイトに掲載する文章の書き方についてはこちら
関連記事Webライティングとは?知れば誰でも書ける!【基礎編】
※補足
筆者は現在、Webライターとして株式会社コンビーズに勤務していますが、前職は某新聞社の記者、某国立博物館では編集員として出版業に関わっていました。過去の経験を踏まえてお伝えしていますので、独自の解釈も含まれています。すべてがあてはまるわけではありませんので、ご了承ください。
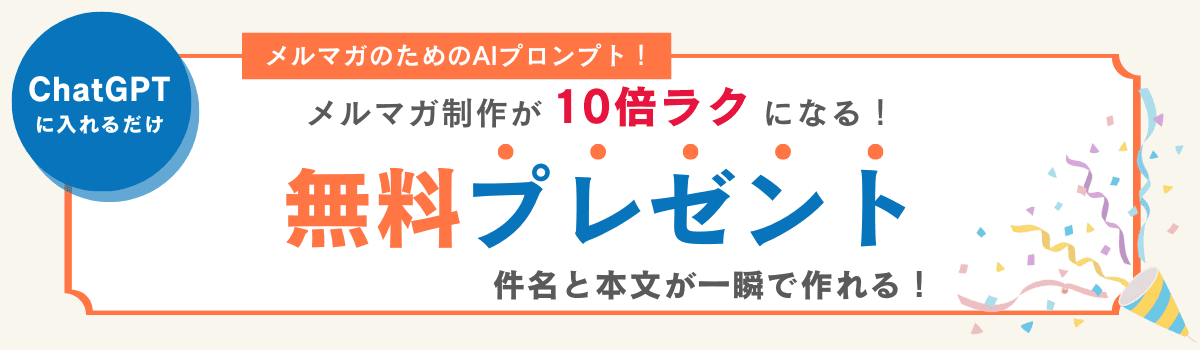
▲メルマガ業務を、出来るだけラクに▲

リッチテキストメールの操作方法についてはこちら
関連記事メルマガの作り方を徹底解説!画像付きのメールはリッチテキストメールで
- 1Webライティングに慣れてきたらやるべきこと
- 1.1表記統一について
- 1.2意識しておくこと
- 1.3検索キーワードの注意点
- 2Webライティング用の書き方
- 3メール配信システムを使おう
- 4まとめ
目次
Webライティングに慣れてきたらやるべきこと
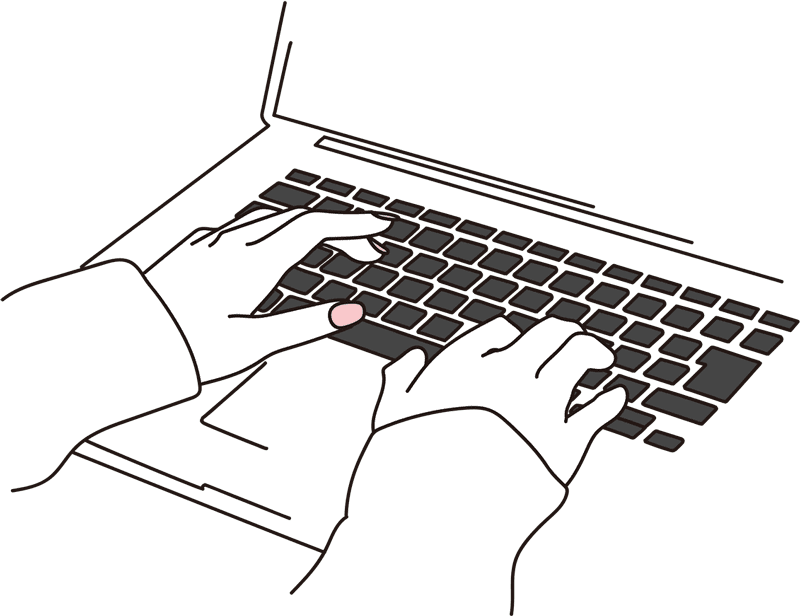
Webライティングに慣れてきた方は、次にユーザーが読みやすい文章を作るための方法を覚えましょう。この段落では、さまざまな「読みやすくするため」のルールを解説します。
表記統一について
Webライティングだけでなく執筆するうえで、重要視されているのが表記統一です。紙媒体では、古くから活用されています。
表記統一は、主に常用外漢字や同音異義語を平仮名にしたり、カタカナ語(外来語と和製英語)をどう表現するかを定めるものです。統一が必要な理由は、見慣れない漢字や言葉が並ぶと、読む側がスムーズに読めない可能性があるからです。
紙媒体では当たり前のように使われている方法のため、読売新聞、朝日新聞、産経新聞、毎日新聞、日本経済新聞は各社で定めた、表記統一のハンドブックを発行しています。 これは日本新聞協会が作った『新聞用語集』をベースに、各社独自の表記統一を加えて出しているものです。
筆者がおすすめするのは、共同通信社発行の『記者ハンドブック』です。こうした手引きを参考にすると、自社オリジナルの表記統一を作ることができます。
公共性の高い文章は、表記統一すると読みやすくなり、ユーザーに親切な記事を提供することができます。
かんたんな表記統一の作り方
ここでは、簡単な表記統一の作り方について解説します。今すぐ、ルールを作成したいという方にはおすすめです。
常用外漢字を使わない
常用外漢字とは、分かりやすくいえば日常であまり使用されない漢字を意味します。国が日常生活で使う漢字として定めたものが常用漢字で、その逆ということです。もちろん、使用禁止というわけではありません。
普段、見慣れない漢字を使うと読みづらい場合があるので、平仮名にしたり類語に置き換えることがあります。
常用か常用外かを調べる方法としては、辞書系のサイトで単語を検索するとわかります。
おすすめは「goo辞書」です。簡潔でとてもわかりやすいです。
単語に▽、▼、×などの印が付いているものは、平仮名にするか、「()まる括弧」にルビを入れて読めるようにするとよいでしょう。
- 信×憑性の場合は「憑」が常用外漢字なので、信ぴょう性か信憑性(しんぴょうせい)とするとよいです。
同音異義語は平仮名表記に
同音異義語はあえて平仮名にすると、間違った使い方を回避できるだけでなく、調べる手間が省けるので、作業効率アップにもつながります。
- 上げる/揚げる/挙げるは同音異義語なので、すべてを平仮名の「あげる」にするとスムーズです。
読点の使い方
読点は、文章を読みやすくするため、またはブレス(息づぎ)のポイントを作るために使います。過剰に打ち込んだり、極端に少ないと読みにくくなるので、感覚的に見て適度な部分に入力していきましょう。
- 悪い例私は、明日の朝に、飛行機に乗って、アメリカへ旅立ちます。
- 良い例私は、明日の朝に飛行機に乗って、アメリカへ旅立ちます。
また、漢字が極端に続く場合も途中で読点を入れて、読みやすくしましょう。
- 悪い例大手食品メーカーの〇〇〇社は〇月〇日自社のセミナールームで、新商品発表会を実施しました。
- 良い例大手食品メーカーの〇〇〇社は〇月〇日、自社のセミナールームで、新商品発表会を実施しました。
意識しておくこと
書くときに2点意識しておくと、ユーザーにていねいな文章を提供できるようになります。
重複を避ける
文章を書いていると、特に漢字が重複することがあります。意味は間違っていないのですが、ユーザーからすると読みづらいものとなってしまいます。
重複を避けるためにも、一段落で同じ漢字を使っている場合は類語などを活用して、意味が崩れないようにしつつ、読みやすい文章にしましょう。
二段落目にも同じ漢字があった場合は、一度段落で区切っているので基本的に問題ありません。
漢字の多用は命取り
これは、ライティングではよくあることなのですが、漢字を多用した文章を書くと「うまく書けている」と勘違いすることがあります。
「漢字をたくさん使った文章を書いたら賢く見える」といった、錯覚に陥りがちになります。
漢字や語彙力はあまり気にせず、まずは自分自身が読みやすいと思える文章作成を心がけましょう。
検索キーワードの注意点
基礎編でも解説したとおり、検索キーワードの選定はメインワードと関連ワードのワンセットで、月間検索数1,500(※)、SEO難易度30前後(※)が、ちょうどよいとされています。ただし、この基準がすべてではありません。書く文章の内容や業界によって、数字は大きく変動します。どういう形で、検索キーワードを取り入れた方が良いかについて解説します。
※「月間検索数」「SEO難易度」については、こちらの記事をご確認ください
ワード別
検索キーワードはビッグワード、ミドルワード、スモールワード、ニッチワードとさまざまな呼び方をします。ただ、一説では明確に区別するのは難しいともいわれています。独自の解釈で必要な検索キーワードを選定して、文章に盛り込みましょう。
※注意
下記、月間検索数もあくまで目安であり、「正確」というわけではありません。
ビッグワード
月間検索数が10,000以上のものを指します。
- 「メール」月間検索数240,800
万一、Googleの検索エンジンで上位に食い込むことができたら、ページビュー数やコンバージョン数の大幅増加が見込めます。
ただ、ポピュラーな単語がほとんどなので、競合他社の利用が多いです。そのため、SEO難易度は高く、上位に昇り詰めるのは至難の業です。
しかし、まったく上位に上がらないという根拠もないので、少々、盛り込んでおくことをおすすめします。
ミドルワード
月間検索数が1,000以上のものを指します。
- 「メール 配信」月間検索数1,280
この場合、ユーザーの検索理由が目的がやや漠然としていますが、ビックワードよりも明確なので、SEO対策上、盛り込んだ方がよいでしょう。
スモールワード
ミドルワードよりも、さらに絞り込んだ検索を行った場合に、呼ばれるものです。
- 「メール 配信 サービス」月間検索数384
この場合、ユーザーは本格的に商品やサービスについて、調べている可能性があります。ターゲット層に刺さりやすいワードとなるので、使用するのをおすすめします。コンバージョン数につながる可能性が高まります。
ニッチワード
あまり使われていない、競合が少ないワードを意味しています。使用頻度が低いため、ニッチワード内で上位を狙うことができます。
月間検索数を調べるとわかりますが、ゼロから1ケタ台のものもあります。ここまで数字が低いと「盛り込む必要がない」と思うかもしれません。検索キーワードの乱用は禁物(後述で説明)ですが、突然トレンドワードになる可能性もあるので、文章に関係性が高いと判断した場合は、盛り込むとよいでしょう。
SEO難易度の見分け方
SEO難易度は、1~10、11~20、21~30…と、10ケタずつ難易度を区切ると分かりやすいです。仮に、月間検索数300に対しSEO難易度70の場合は無理に取り入れず、月間検索数1,000に対しSEO難易度10なら使った方がよいとさえています。ここも、検索キーワードを盛り込む側のさじ加減で考えるとよいです。
流れ(推測)
ブログやサイトのSEO効果が表れるまでには、4カ月~1年はかかるといわれています。
仮に、ある検索キーワードの効果が発揮されて、Google(検索エンジン)の検索結果に表示されたとします。SEO難易度が高い場合は、いかにGoogleの高評価を得て、上位にランクインできるための入念な計画が必要となります。
難易度が高ければ高いほど、コンテンツを充実させなければ、上位には入れない可能性があります。
詰め込みは禁物
基礎編でも解説したとおり、特定のキーワードを多く詰め込んだところで、順位変動に影響はないとされています。
逆に、やり過ぎてしまうと、Googleの検索エンジンがスパム対象と判定し、ペナルティとして評価を下げる可能性があるともいわれているので、適量にしておくことをおすすめします。
SEO対策で覚えておくべきこと
ひと昔前は、強引に検索順位に上がるようにするために、悪質なSEO対策が横行していた時期がありました。
一例として、見たことがある方もいるかもしれませんが、検索キーワードを大量に文章の一番下などに羅列して、なおかつ文字の色を背景と同じ色にして隠すといった行為をしている、悪質なサイトもありました。
これらの行為を、ブラックハットSEOといいます。主に禁じ手とされている例として、下記のようなものがあります。
- むやみにリンクを貼り付ける
- 文章の大半をコピー&ペーストで量産する
- 検索キーワードやリンクを隠して掲載
- 必要以上に検索キーワードを詰め込む
- ユーザー向けとは別に検索エンジン用のページを表示させる
数十年にわたり、Googleの検索エンジンのアルゴリズムも成長しているため、禁止事項が増えているのはあたり前です。
現在は、ホワイトハットSEOが主流となっており、サイトがユーザーにとって豊富なコンテンツを用意しているかや、理解しやすい情報発信を行っているかが重要となっています。
Webライティング用の書き方
Webライティングには独特な書き方があり、SDS法、PREP法、PASONAの法則といったものがあります。
SDS法
SDS法で書く場合は
- 全体の概要(Summary)
- ↓
- 詳細説明(Detalis)
- ↓
- まとめ(Summary)
の順番になります。コンパクトに結論をまとめているので、ユーザーにダイレクトに伝えたいことを発信することができます。
PREP法
PREP法で記事を書く場合は
- Peoblem(問題)
- ↓
- Affinity(親近感)
- ↓
- Solution(解決策)
- ↓
- Narrow down(絞り込む)
- ↓
- Action(行動)
の順番になります。例としてECサイト(通販サイト)向けに、サービスを提供したい記事を書くとします。
- 問題ECサイトの離脱で困っている
- 親近感離脱が増えると売上が落ちてしまい困っているのでは?
- 解決策当社のWeb接客を導入すれば離脱防止につながります
- 絞り込む今なら永久無料プランあり、コンサルがサポートします
- 行動もう一度Web接客の有効性を書く(まとめ部分)
というように、ユーザーに対し「こんな課題を抱えていませんか?解決策はコレです。ぜひ導入してくださいね」という一連の内容を書くことができます。これらの効果により、コンバージョン数増につながる可能性があります。
メール配信システムを使おう

今回は、Webライティングの書き方についてご紹介しました。基礎、応用を知ると、ブログやサイト、メール配信と媒体を問わず、文章を作成することができます。
ぜひ、この機会にメール配信システムを導入して、覚えたライティングで文章を作り、メール配信をやってみませんか?
当社が提供するCombz Mail PLUS(コンビーズメールプラス)は、大量のメールを高速かつ確実に配信することができるだけでなく、分析ツールも備わっているため、メールマーケティングも行うことができます。
さらに、文章の書き方に困ったときや、新たなアイデアなどが欲しいという方のために、当サービスサイトでは「メール作成」として、いろんな活用方法を記事として掲載しています。
まとめ
今回は、前回の『Webライティングとは?知れば誰でも書ける!【基礎編】』に続き、応用編を解説しました。
Webライティングは、そう難しいものではなく、一定のルールを覚えることで習得ができます。そのため、市場としては参入しやすいため、副業としてもWebライティングは人気があり、多くの方々がさまざまな執筆を行い、生業としているくらいです。
ライティング方法さえつかんでしまえば、あとは「誰にどんなことを伝えたいか」だけをしっかり抑えておけば、どんな文章であっても読む側は理解を示してくれます。
ぜひ、今回の記事をきっかけにチャレンジしてみてくださいね。以上、『Webライティングとは?実際に書いてみよう!【応用編】』でした。
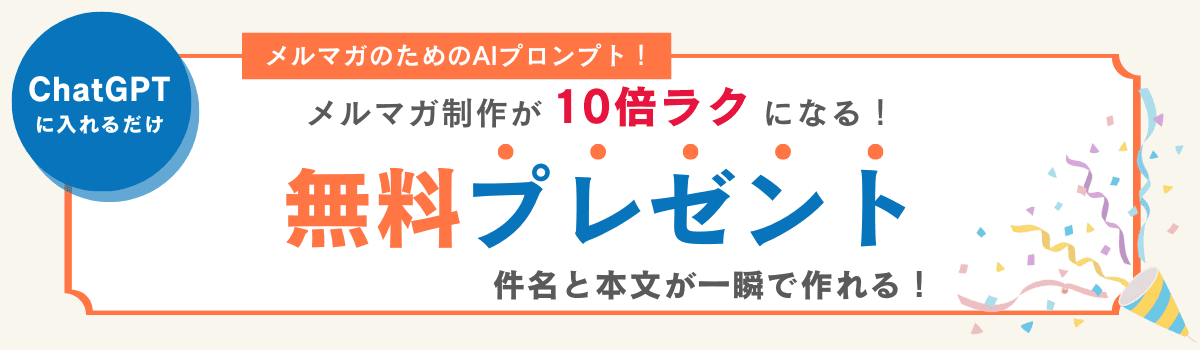
▲メルマガ業務を、出来るだけラクに▲
資料請求・お問い合わせ
料金プランや運用のご相談まで、あなたの専属コンサルタントがサポートします
パートナー制度
コンビーズのサービスをご紹介していただくと、あなたも紹介者さんもおトク
セキュリティ
お客様が安心してご利用いただけるようセキュリティ対策もバッチリ。第三者認証であるISMS(ISO27001)を取得済み。