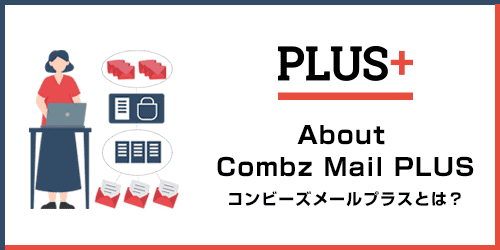【学習塾向け】塾生への連絡・お知らせ・相談対応や連絡先管理にメール配信
2023年03月14日
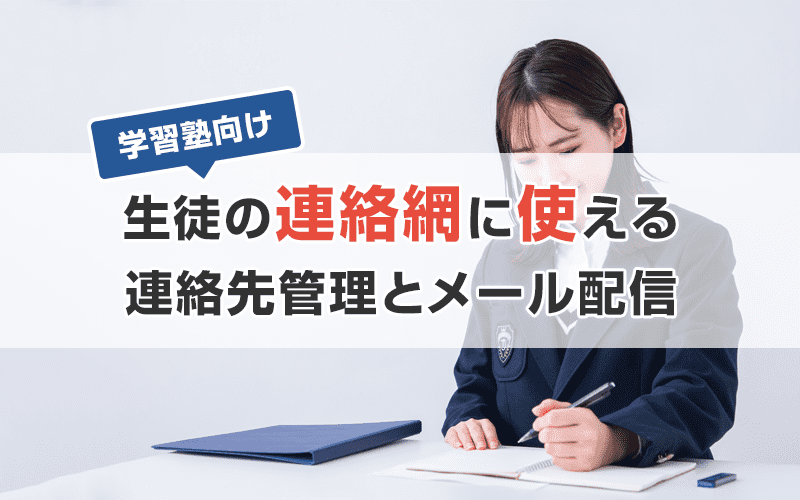
基本的に塾では、保護者への連絡方法の大半が電話となっています。
しかし、保護者側はメールやSNSでの連絡を望んでいるのをご存知でしたか?
特に使い勝手がいいのはメールで、理由としてはパソコンやスマートフォンを持っているのであれば、確実に全員が「メールアドレス」を最低1つでも所持しているためです。
そこで今回は『【学習塾向け】塾生の連絡・お知らせ・相談対応や連絡先管理にメール配信!』と題し、メール配信システムを使った連絡方法を紹介します。
メール配信システムは連絡網として役に立ちます。
使うことで学習塾に在籍している塾生や保護者に対し、入退室の連絡、塾に関するお知らせ情報のほか、個別相談などを、円滑に行うことができます。
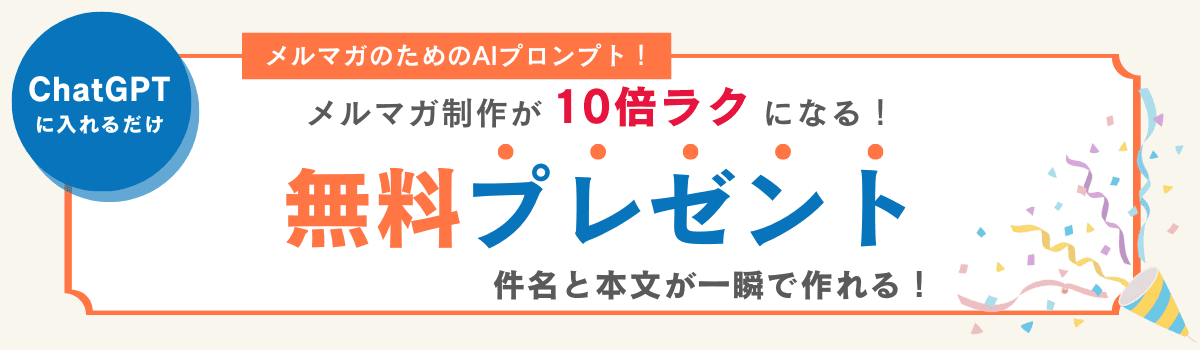
▲メルマガ業務を、出来るだけラクに▲

「メルマガの読者像を想定する」「メルマガ登録者を増やすための集客方法」「メルマガを運用するにあたっての目標設定」などについてはこちら
関連記事メルマガの始め方が分からない!初心者でもすぐにできる事前準備とは
塾とメールの関係「連絡網に使ってほしい」
学習塾側が保護者などへ連絡する場合、電話やメールのほかSNSといったさまざまなツールを活用しているかと思います。
では、実際に各ツールでの連絡の割合はどんな感じなのでしょうか?
この段落では、株式会社POPER(出典:Comiru調べ)が行った調査(保護者300人、学習塾70教室対象)を参考例に、「連絡方法」の実態を紹介します。
理想の塾からの連絡方法:1位「メール」2位「LINE」
『現在子どもが通っている学習塾での連絡手段』(保護者300人複数回答)の調査によると、47.7%がメール、46.3%がLINEでの連絡が理想と、保護者側は考えているそうです。
しかしながら実際の運用としては、メールは52.0%と現実が理想を上回っており、LINEは25.3%と現実が理想を下回っています。
メールに関しては、現実が理想を上回る結果となり、ニーズにある程度応えられているのがわかります。
しかし、実際には大多数の学習塾が今でも電話を連絡手段としており、実際の運用では65.7%となっています。
電話連絡を理想としている割合は33%で、保護者の望まない結果となっているようです。
株式会社POPERの調査結果としては、
保護者の要望に学習塾側が対応しきれていない
ということがわかります。
【考察】塾からの連絡にメールが支持される理由
塾からの連絡手段にSNSよりもメールが選ばれるのは、
- 必ずパソコンやスマートフォンにメーラー(メールを送受信するツール)が導入されている
- 1人1アドレスは所有している
- SNSは全員が導入しているとは限らない
というのが理由として考えられます。
また、SNSはプライベート用、メールは業務的なものに使うといった区別をしたいという、ユーザーも潜在的に存在している可能性があります。
プライベートと業務的な連絡を1つのツールにまとめてしまうと、誤操作で予期せぬ情報を漏らしてしまう可能性もあります。
そうしたトラブルを回避するためにも「連絡方法としてメール」を望む人がいるのかもしれません。
保護者や塾生の連絡にメール配信システム
学習塾を運営している方なら、一度は、
「 円滑に保護者や塾生に情報を発信したい 」
と考えたことがあるのではないでしょうか?
仮に、既存のメーラー(OutlookやGmailなど)からBCCを使って一斉送信しているのであれば、この方法はおすすめしません。
個人情報漏えいや一時的なメール送信の停止など、リスクを伴うためです。
リスクについては、下記リンクを参照ください

CCやBCCの基本的な解説や、BCCを使用した一斉送信の危険性について
関連記事社内メールやメルマガをBCCで一斉送信するとどうなる?
そこで推奨するのが、メール配信システムの導入です。
メール配信システムを使うと、保護者や塾生への連絡網として使用できます。
塾への入退室管理システム代わりにメール配信
塾の授業は学校が終わってからになるため、夕方~夜の日没後の暗い時間に通うことが多くなります。
暗いと見通しも悪くなるため、不審者に気づくことができなかったり、交通事故に遭うリスクが高まります。
特に小中学生は塾の帰りに事件に巻き込まれやすくなります。
保護者としては、無事に塾へ着いたのか、塾を出てから無事に帰ってこれるか心配になるものです。
ここで、保護者と塾でマメに連絡を取ることができれば、
保護者も安心し塾との信頼関係を築くことができます。
生徒の行き帰り以外に近所に不審者が現れた時の情報共有などにも役立つので、子どもの安全対策にもなります。
塾発信で「緊急連絡」する場合は一斉メール配信
緊急時の連絡手段として、電話するよりも、メールを一斉配信する方が早く確実に連絡できます。
最近は、固定電話を引いてない家庭も少なくありません。
この場合、電話連絡は保護者の携帯電話に掛けることになりますが、いつでも直ぐに電話に出られるとは限りません。
仕事中や家事の忙しい時間帯に掛けてしまうと、保護者と連絡が取れません。
また、緊急連絡の連絡として多いのは、台風などの災害時です。
メールで早急に連絡することで、通塾することを防げるため、生徒の安全を守ることができます。
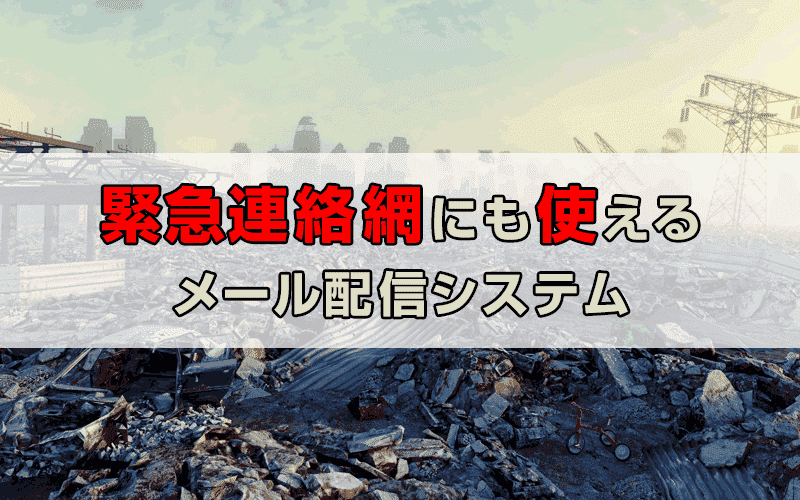
災害時の緊急連絡網としての使い方についてはこちら
関連記事災害時の緊急連絡網にメール配信システムを活用
授業の補足や豆知識の配信で好印象
学習塾の授業だけでは、全てを教えきれないこともあります。
そこで補足としてメール配信でフォローすると、細かいところまで見てくれているという印象を持ってもらえます。
授業の内容の他には、
学力向上のための豆知識を配信するのも効果的です。
せっかく学習塾で教わっても、自分から勉強しないと成績は上がらないものです。
勉強方法が分からない生徒を助けるつもりで助言してみましょう。
保護者との面談やクレーム対応
保護者からの面談やクレーム対応も、大幅に時間を取られてしまいます。
また、学習塾は学校と違い塾の効果として、生徒の成績の向上が最も重要となります。
特に成績が落ちた場合のクレーム対応は、慎重にならざるを得ません。
このような状況が重なると、業務時間だけでなく、塾講師自身の仕事のモチベーションも低下し悪い口コミにつながってしまいます。
保護者からのクレームを100%無くすことは、難しいですが、少なくとも日ごろから、メール配信システムを活用し保護者と連絡を定期的に行うことで、クレーム発生率を軽減することが期待できます。
アンケートを導入して塾の評判を上げる
アンケートを導入して塾の評判を上げる
メール本文にURLを設置することで、あらかじめ設定したアンケートのページへと遷移することができます。
例えば…
- 授業のペースは問題ないか?
- 授業の時間は適切か?
- 空調は適切か?
- 改善してほしい授業内容
- その他、要望点
このように子供や保護者の生の声を聞くことができます。
集計結果はグラフ表示により見やすくなっているため集計もとりやすく、教室の改善活動にもつなげられます。
学習塾の現状、伴う集客方法
2022年は首都圏と関西圏で、中学受験がブームになっているといわれています。
首都圏での2022年入試の受験者数は、私立と国立の中学生を合わせて5万1,100人で、1991年の5万1,000人を上回ったそうです。
関西も中学受験の受験者数は下回るものの、受験率は前年と比べて0.1ポイントアップし9.74%になったとのことです。
少子化のなかでも情勢の変化で学習費にお金をかけたり、減らしたりと波はありますが、こうしたトレンドをうまく押さえつつ、宣伝活動をすれば集客につながる可能性があります。
学習塾に学生を集客する宣伝方法
学習塾は基本的に地域密着型のため、小規模の商圏で集客を行っているかと思います。
コミュニティが狭いほど、口コミといった古典的な宣伝方法が有効な可能性があります。
この段落では、改めて定番化している宣伝方法について解説します。
リアル面での塾への集客方法
まずは、口コミやチラシなど、リアル面での宣伝方法について解説します。
- 口コミで評判を広げる
- 主に、講師の評判、成績アップ、志望校合格などの成果が高ければ高いほど、評判が口コミで広がり、それらを聞いた保護者らが、自身の子どもを入塾させる可能性があります。保護者同士のネットワークをうまく活用することで、周知してくれます。
- チラシの配布で周知する
- チラシも配布する時期を、間違えなければ効果があります。
例えば、実力テストや中間・期末テスト前のテスト対策、予習や復習ができる夏季講習、冬季講習を夏休み・冬休み前にチラシで宣伝することで、それを見た保護者や学生が入塾する可能性があります。ただ、チラシ配布の場合、高い経費がかかるので、コストや費用対効果を検討する必要があります。
メール配信とチラシ配布のコスト差については、下記リンクで詳しく解説しています。
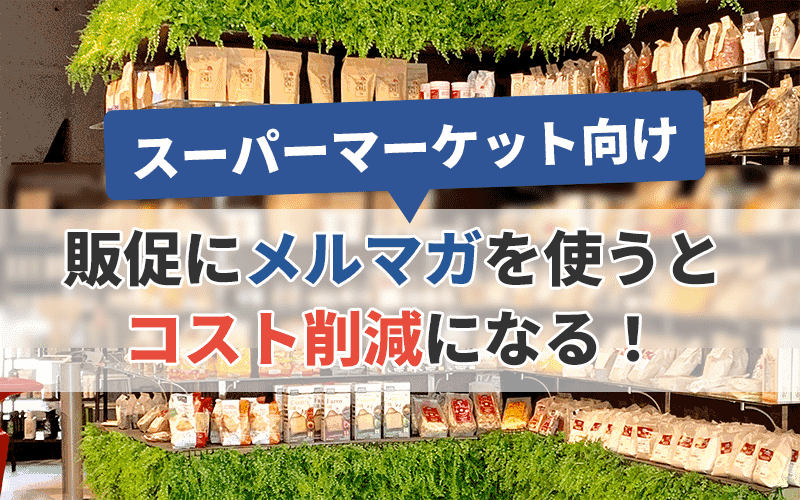
コストを抑えて既存で使っている宣伝媒体とメール配信システムを、うまく併用する方法についてはこちら
関連記事【スーパーマーケット向け】販促にメルマガを使うとコスト削減になる!
- 看板を設置し存在をアピール
- 看板を設置することで、学習塾があることをアピールすることができます。学習塾の前を通る保護者などの目にとまれば、存在を知ってもらえるだけでなく、ふとしたときに入塾させたい学習塾の1軒として、検討してくれる可能性があります。
- 体験授業をする
- 教室の雰囲気や、どんな流れで授業が進行しているかなどを、体験授業で知ってもらうのも、入塾のきっかけとなります。学生にとって、教室の環境やカリキュラムがマッチするのであれば、入塾につながる可能性があります。
Web媒体を介しての塾への集客方法
次にインターネットを利用しての宣伝方法についてです。
- ホームページ・ブログ・ポータルサイトを活用
- 今ではほとんどの学習塾が、自らのホームページやブログを立ち上げていたり、ポータルサイトに登録したりし、インターネットを介しての宣伝を行っているはずです。ホームページなどを作成し、対象年齢や授業内容のほか、月謝、住所、連絡先などを情報として公開しておくことで、検索にヒットした保護者が問い合わせをしてくる可能性があります。
- SNSで情報を拡散
- SNSからの情報収集は一般化しています。SNSで授業の様子や講師の紹介などを積極的に行い、不特定多数の保護者の目にとまるようにすると、宣伝効果を発揮します。ただ、地域密着を考えると不特定多数への宣伝は、うまく地域がマッチしにくい面があるので、ハッシュタグで地域名などを付けて、エリアを絞って拡散できるようにしましょう。
- Web広告を出稿する
- Googleにリスティング広告(検索連動型広告)を出稿するのも、一つの方法です。リスティング広告とは、ユーザーが検索したキーワードにより、表示されるテキスト広告を指します。リスティング広告を出稿することで、GoogleやYahooの検索結果上位に表示されます。検索キーワードに費用が発生します。

Webマーケティングの販売促進や集客についてはこちら
関連記事Webマーケティングとは?初心者向けに基礎知識から実践まで簡単に説明
- ステップメールで塾の情報を発信し興味をひかせる
- メール配信システムには「ステップメール機能」が備わっています。このステップメールを使うことで、最低限知っておいてほしい塾に関する情報を、自動でメール配信することができます。ステップメールとは、ユーザーの行動(アクション)を起点に、あらかじめ準備しておいたメールを、事前に設定したメール配信を実施する日時に数回、自動的に行うことができるものです。
例えば、PDFで閲覧可能な資料を作成しているとします。
ホームページ内で資料請求を行っているとし、実際に申し込みがあったのを起点としたとします。
- 当日資料請求に関するサンクスメールを送る
- 2日後PDF形式の資料をメール配信する
- 3日後塾の雰囲気や実績のほか塾生の声を届ける
- 4日後体験学習の案内などの問い合わせメールを送る
といった流れで少しずつ、保護者や学生に対し情報を自動でメール配信することができるので、24時間年中無休の営業マンとして活躍します。

ステップメールとは何か、どのように活用すればいいのかの方法についてはこちら
関連記事ステップメールとはなにか?ツールとして活用し集客&購買意欲を高める
まとめ
今回の記事はいかがでしたでしょうか?
本記事では、学習塾でのメール配信システムの活用例を紹介しました。
メール配信システムを利用することで、保護者や塾生へ塾に関する情報発信、連絡網に使うことができます。
また、メーラーのBCCと違い、メール配信システムはセキュリティ対策が万全なため、個人情報漏えいや配信停止などのリスクを負うことはありません。
ぜひ、連絡網にメール配信システムの導入を、検討してみてくださいね。
以上、『【学習塾向け】塾生の連絡・お知らせ・相談対応や連絡先管理にメール配信!』でした。
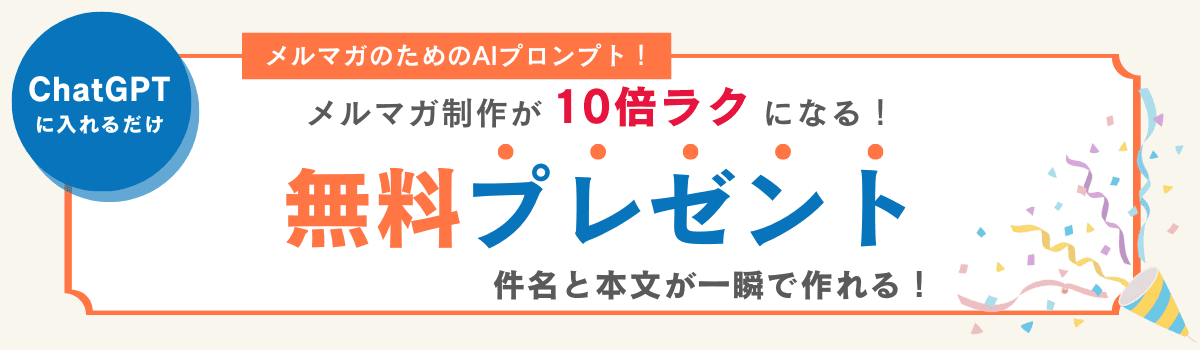
▲メルマガ業務を、出来るだけラクに▲
資料請求・お問い合わせ
料金プランや運用のご相談まで、あなたの専属コンサルタントがサポートします
パートナー制度
コンビーズのサービスをご紹介していただくと、あなたも紹介者さんもおトク
セキュリティ
お客様が安心してご利用いただけるようセキュリティ対策もバッチリ。第三者認証であるISMS(ISO27001)を取得済み。